
渋谷区と歩んだ半世紀、さらなる街の発展を願う。
令和6年(2024年)10月15日号
渋谷区でさまざまな役職を歴任し、今年8月に渋谷区名誉区民に顕彰された大高満範さんに、これまでの多岐にわたる活動や渋谷区への思いについて伺いました。
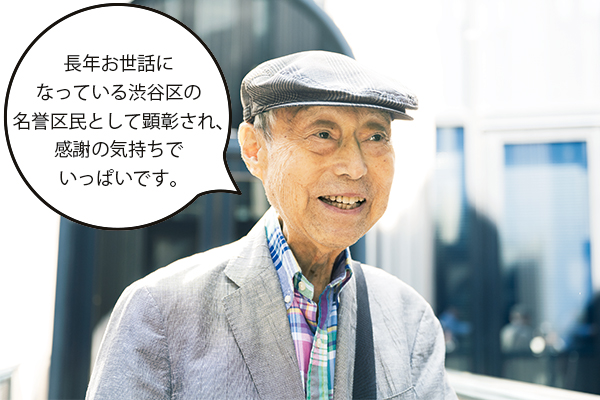
大高満範さんプロフィール
昭和9(1934)年生まれ、広島県出身。弁護士としての豊富な経験を生かし、渋谷区教育委員会委員、同委員長をはじめ、渋谷区法律・交通事故相談員、渋谷区議員報酬等及び区長等給料等審議会会長、渋谷区住環境整備審議会会長、渋谷区ホテル等建築審議会会長、渋谷区青少年問題協議会委員、渋谷区奨学資金運営委員会委員、渋谷区民生委員推薦会委員、渋谷区立千駄谷小学校学校運営協議会委員など、幅広い分野で渋谷区のまちづくりや公共福祉、教育行政、学校を中心とした地域コミュニティーの発展に貢献。さらに、公益財団法人渋谷区文化・芸術振興財団の理事長として、区民の文化芸術を享受する環境の整備に大きく寄与。令和6(2024)年8月、渋谷区名誉区民顕彰。大高霧海という俳号で俳人としても活動中。

弁護士としての知見を生かし、まちづくりや教育行政に携わる
大高さんの自己紹介をお願いします。
大高:昭和9(1934)年生まれで、今年で90歳になりました。高校生まで広島県三次(みよし)市で過ごし、大学進学時に上京しました。渋谷区に住むようになったのは、30歳を過ぎて結婚したタイミングでしたね。区には50年以上お世話になっています。
当時の渋谷区の印象を教えてください。
大高:上京した頃は杉並区に住んでいましたが、京王井の頭線を利用して、渋谷駅周辺にはよく訪れていました。当時はまだ日本全体の治安が安定しておらず、渋谷駅周辺の開発も進んでいない状況でした。その後、国道や高速道路などの交通面の整備が進むにつれて、街の印象もどんどん良くなっていきました。
渋谷区でのこれまでの活動について教えてください。
大高:40代に入った昭和50(1975)年ごろから、弁護士として渋谷区の法律顧問を担当しました。渋谷駅周辺の開発における建築物の許認可に関するサポートをしたり、区の委員会に出席して法律面でのアドバイスなどをしたりしているうちに、区での役割が徐々に増えていきましたね。自分がまちづくりに関わりながら、区の発展を肌身で感じてきたので、現在のにぎやかな街の様子には感慨深いものがあります。
渋谷区のまちづくりに期待していることはありますか?
大高:渋谷区は住宅街と繁華街のすみ分けが進んでいますが、進行中の渋谷駅前の大規模再開発が完了することで、より一層住みやすい街になるはずです。関係者の皆さんもとても努力されていますので、今後も期待したいですね。
弁護士としての活動以外にも、渋谷区教育委員会の委員として2期8年、その間には委員長も二度務めていらっしゃいました。
大高:まちづくりと教育行政は関連性が高いと感じていて、区の発展につながるのであれば、なるべく関わる分野を限定せずに尽力したい気持ちがありました。私が委員だった頃は、小中学校の義務教育の在り方についての議論が活発で、当時はまだ、小学校と中学校の間で一貫した教育制度がなかったため、各学校の先生たちとも相談しながら制度を組み立てました。また、安全面に懸念がある区内の通学路を整備するため、意見を出し合い、改善に努めました。私たちが環境を改善することで、子どもたちには安心して学校生活を送ってほしいと思っていました。
文化芸術への活動にも尽力し、渋谷区名誉区民に
まちづくりや教育行政に携わる一方で、公益財団法人渋谷区文化・芸術振興財団(以下、文化・芸術振興財団)の理事長職を約8年務められました。文化芸術の分野にも関心をお持ちだったのでしょうか?
大高:昔から絵画や彫刻などに関心があり、芸術作品に触れる時間も多くありました。弁護士の仕事は物事と合理的に向き合う時間が多いため、そのような時間以外では、自分の感情や感受性を自由に育むための時間を過ごしたかったんです。教育委員長を退任したタイミングで、文化・芸術振興財団の理事長職の打診をいただいて、渋谷区の文化芸術の振興と発展にも寄与したいという思いで引き受けました。
理事長をされていた際に印象に残っていることはありますか?
大高:令和3(2021)年に渋谷区立松濤美術館が開館40周年を迎えたのですが、美術館の設計者である白井晟一(しらいせいいち)さんの記念企画を実施できたことは、とても印象深い思い出です。任期中は自分からも積極的に企画を提案し、美術館の館長、副館長、学芸員の皆さんなどと意見交換を重ねながら、展覧会の企画や地域との連携に励みました。
これまでの活動の功績がたたえられ、今年8月に渋谷区名誉区民に顕彰されました。おめでとうございます!今のお気持ちをお聞かせください。
大高:ありがとうございます。名誉区民に選ばれたという連絡が届いた時、ちょうど病院から退院したばかりで、とても驚きました。長年お世話になっている渋谷区に貢献したいという思いでさまざまな活動を続けてきたので、感謝の気持ちでいっぱいです。名誉区民に選ばれたことで、生活が変わったということはありませんが、区の発展のために貢献できる機会があれば、今後も尽力していきたいです。
およそ半世紀にわたって、さまざまな活動を続けていらっしゃいますね。健康を維持するための秘訣(ひけつ)はありますか?
大高:朝と夕方の2回、近所を散歩する日課はありますが、健康維持や体力づくりのために、そのほかで意識していることは特にありません。基本的なことかもしれませんが、忙しい時でもなるべく徹夜はせず、規則正しい生活を心掛けています。もしかしたら、自分が好きな俳句の活動をずっと続けていることが、健康の秘訣なのかもしれません(笑)。
心に余裕を持ち、文化芸術に触れることが、街の発展につながる
現在はどのような活動をされていますか?
大高:これまでいろいろな役職を務めてきましたが、90歳で引退すると決めていたため、今年3月をもって区に関連する全ての役職を退任しました。弁護士事務所で就いていた役職も後継者に引き継ぎ、最近では、会議などに呼ばれた時だけ顔を出して、たまにアドバイスをする程度です。引退はしましたが、私にできることがあればいつでも協力する姿勢を大切にしています。現在は趣味の俳句に時間を費やす日が多いですね。
俳句を始めたきっかけや俳人としての活動を教えてください。
大高:高校生の頃から興味はありましたが、本格的に俳句を詠むようになったのは40歳を過ぎた頃です。昭和60(1985)年に俳句の雑誌を発行する「風の道」に入会し、現在は団体の主宰を務めています。また、国際俳句協会の会長として、俳句をユネスコ無形文化遺産に登録してもらえるよう、その普及活動にも取り組んでいます。大高霧海(おおたかむかい)という俳号で活動していまして、その名前は、故郷の三次市でも有名な霧の海の景色から着想しました。
大高さんは、しぶや区ニュース「くみんの俳句」で応募作品の選者も担当されています。選評する時に大切にしていることを教えてください。
大高:「くみんの俳句」のコーナーは今年で10年目を迎えました。選評する時に意識していることは、写生(注)がどこまで徹底されているかということですね。詠んでいる人の目がどこまで行き届いているかを選句の基準にしています。
(注)実物・実景をありのままに写し取ること。
俳句などの文化芸術に関心を持ち続けるために、心掛けていることはありますか?
大高:日々の生活にできるだけ余裕を持たせることです。ただ、勉強や仕事に追われてしまったり、何かとせわしなく、落ち着いて休む暇もなかったりする現代社会で、それを実践することは難しいと感じる人もいるかもしれません。そのような場合は、たとえば通学や通勤などの移動中に一句だけ考えてみる、創作はせずとも、休日に絵画などの芸術作品を鑑賞する時間を確保するなど、些細(ささい)なことでもいいので、生活の中で文化芸術に触れるための余裕をつくってみてほしいです。
最後に、区民の皆さんに向けてメッセージをお願いします。
大高:文化芸術への意識の向上を目標として、私はこれまでさまざまな活動に取り組んできましたが、区民の皆さんはその意識がとても高いと感じています。これからも興味を持ち続けながら、ぜひ、その楽しさを感じてほしいです。文化芸術への関心が高まることで、渋谷区全体が発展することを願っています。
「渋谷のラジオ」で放送中!
大高さんへのインタビューは10月15日・22日・29日に「渋谷の星」で放送します。
渋谷のラジオ87.6MHz(外部サイト)
令和6年(2024年)10月15日号
他のページを見る
