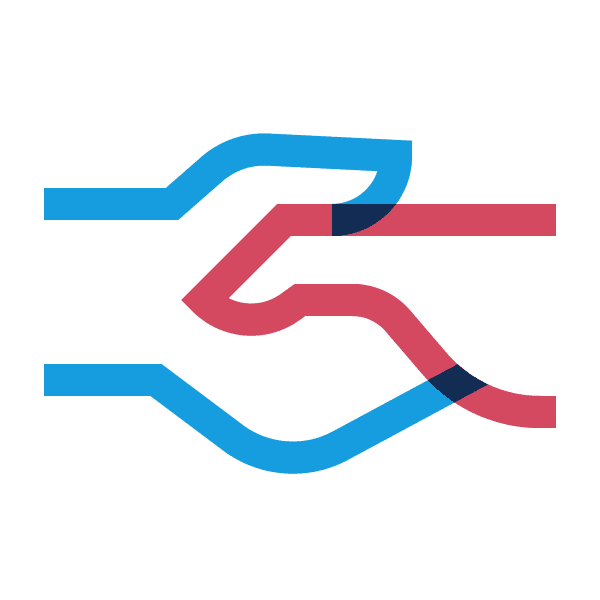お知らせ
2025年8月1日
現在、高校2年生相当の女性のHPVワクチンの法定接種期間は令和7年3月31日で終了いたしました。 HPVワクチンは3回接種が必要なワクチンであり、最短のスケジュールでも4ヵ月の期間が必要となります。 キャッチアップ接種期間中(令和4年4月1日~令和7年3月31日)に1回以上接種をした人を対象に令和7年4月1日以降も公費による接種が延長されます。詳しくは【積極的な勧奨の差し控えによりHPVワクチン(子宮頸がんワクチン)の接種機会を逃した人への対応「キャッチアップ接種」】のページをご覧ください。
2025年4月1日
麻しん風しん混合(MR)ワクチンの供給不足などにより、ワクチンの接種が出来なかった人を対象に接種期間が令和9年3月31日まで延長されることになりました。対象者には、5月上旬にお知らせの送付を予定しています。詳しくはページ中段「麻しん風しん混合(MR)ワクチン 接種期限延長について」をご覧ください。(注)期限切れの予診票は使用できません。
定期予防接種とは
定期予防接種は予防接種法に基づく予防接種で、対象者は受けるよう努めなければならないとされています。法定接種期間であれば、決められた回数を無料で受けることができます。
(注)長期にわたる疾患などでやむを得ず、定期予防接種を法定接種期間内に受けることができなかったと認められる場合は、予防接種が受けられるようになってから2年間、定期予防接種として接種することができます。詳しくは、長期にわたる疾患等で、やむを得ず法定接種期間を超えてしまった場合のページをご覧ください。
法定接種期間の数え方
- 「生後2月から90月に至るまでの間」とは、生後2か月に応当する日の前日から、生後90か月(7歳6か月)に応当する日の前日までのことです。
- 「応当する日」とは、誕生日と同じ日付のことです。
- 「11歳以上13歳未満」とは、11歳の誕生日の前日から13歳の誕生日の前日までのことです。
【例】平成25年2月20日生まれの場合
- 「生後2月から90月に至るまでの間」平成25年4月19日~令和2年8月19日
- 「11歳以上13歳未満」 令和6年2月19日~令和8年2月19日
渋谷区に転入した場合・予診票を紛失した場合
渋谷区へ転入後は、渋谷区以外で発行された予診票は使用できません。通知送付時期を過ぎてから転入した場合および予診票を紛失した場合は、渋谷区の予診票を発行しますので、母子健康手帳など接種歴が分かるものをご用意のうえ、下記1~3のいずれかの方法でご申請ください。
(注)本申請は法定接種期間のみの定期予防接種予診票の発行手続きとなります。なお、法定接種期間を過ぎた場合でも、予診票の発行が出来る場合があります。詳しくは予防接種係までお問い合わせください。
1.電子申請 | 2.電話 | 3.来庁 |
|---|---|---|
地域保健課予防接種係へ電話 電話番号:03-3463-1412 (注)土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く | 本庁舎7階 地域保健課予防接種係にて申請 その場で予診票の受け取りを希望する場合は保護者の人の「本人確認書類」をお持ちください。 (注)18歳以上の人で本人以外が予診票の受け取りを行う場合は「代理人自身の本人確認書類」と「委任状」が必要となります。 委任状には指定の様式はありませんが、次の様式をダウンロードしてご使用いただくこともできます。 |
予防接種による副反応について
予防接種の種類によっても異なりますが、接種後に熱が出たり接種した部分が腫れたりすることがあります。
ほとんどは数日以内に自然に治りますが、まれに高熱やひどい腫れ、ひきつけなどの症状を起こすこともあります。接種後にこうした症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診してください。
予防接種後の重い副反応については、報告基準が定められていて、基準にあてはまる症状を診断した医師は、国に報告することとされています。
なお、こうした重い副反応について、被接種者や保護者から報告することもできます。地域保健課予防接種係までご相談ください。また、定期予防接種により引き起こされた副反応により、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度により、一定の給付が行われる場合があります。
保護者以外の同伴について
委任状・同意書
16歳未満の人が予防接種を受けようとする際は原則、保護者(予防接種法において、親権を行う者または後見人のこと)の同伴が必要です。
諸事情で保護者以外の人が同伴する場合、または13歳以上16歳未満のお子さんが一人で接種を受けに行く場合は次の書類をご使用ください。
(注)必ず予診票の保護者署名欄も事前にご記入ください。
該当事項 | 書類 | 注意事項 |
|---|---|---|
保護者以外の人が同伴する場合 | 同伴する人は普段からお子様やご家族の健康状態をよく知っている人にお願いをしてください。 | |
13歳以上16歳未満のお子さんが一人で接種を受ける場合 | 保護者が区から配られている説明書をよく読み、理解・納得した上で、一人で予防接種を受けさせることを希望するときにご使用ください。 |
接種場所
接種場所は23区内の契約医療機関です。
(注)BCG、不活化ポリオ、子宮頸がんについては、それぞれの項目をご覧ください。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
定期予防接種の種類
- 子どもの予防接種一覧表(令和7年4月1日現在)(PDF 273KB)
- 小児用肺炎球菌ワクチン
- B型肝炎
- ロタウィルス
- 5種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ、ヒブ)
- 4種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ)(注)5種混合を接種した場合は、接種不要なワクチンです。
- ヒブ(注)5種混合を接種した場合は、接種不要なワクチンです。
- 急性灰白髄炎(ポリオ)(注)4種混合または5種混合を接種した場合は、接種不要なワクチンです。
- BCG
- 麻しん風しん混合(MR)
- 水痘(水ぼうそう)
- 日本脳炎
- DT二種混合(ジフテリア、破傷風)2期
- 子宮頸がん予防ワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン)
小児用肺炎球菌
接種開始時期により、接種スケジュールが異なります。詳しくは、小児用肺炎球菌ワクチンのお知らせ(PDF 764KB)をご覧ください。
(注)令和6年10月1日から、小児肺炎球菌ワクチンは15価から20価に切り替わりました。既に13価ワクチンで接種を開始している人は、20価ワクチンに切り替えて接種することとなります。15価ワクチンで接種を開始している人は、原則15価ワクチンで接種を完了していただきます。詳しくは、医師にご相談ください。
法定接種期間 | 標準的な接種期間と接種回数 | 予診票の送付時期 | 場所 |
|---|---|---|---|
生後2か月から60月に至るまでの間 | 生後2か月~7か月に至るまでの間に接種開始し、27日以上の間隔をおいて3回接種。 3回目接種後、60日以上の間隔をおいて1回接種。 | 生後1か月に達した月末に送付 | 23区内契約医療機関 |
B型肝炎
詳しくはB型肝炎ワクチンのお知らせ(PDF 527KB)をご覧ください。
(注)HBs抗原陽性の妊婦から生まれた乳児として健康保険により出生後にB型肝炎ワクチンの投与(抗HBs人免疫グロブリンを併用)の全部または一部を受けた人は除きます。
(注)任意接種としてすでに接種を受けた回数分は定期接種を受けたものとみなし、残りの回数分が対象となります。
標準的年齢(法定接種期間) | 標準的な接種期間と接種回数 | 予診票の送付時期 | 場所 |
|---|---|---|---|
生後1歳に至るまで | 生後2~9か月に至るまでの間に、3回接種(27日以上の間隔で2回接種後、1回目から139日(20週)以上あけて1回接種) | 生後1か月に達した月末に送付 | 23区内契約医療機関 |
ロタウイルス
詳しくは、ロタウイルスワクチンのお知らせ(PDF 2,049KB)をご覧ください。
(注)初回接種は標準的には生後2か月から14週6日までに接種します。
種類 | 法定接種期間 | 標準的な接種期間と接種回数 | 予診票の送付時期 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
ロタリックス | 生後6週から24週まで | 27日以上の間隔をあけて2回接種 | 生後1か月に達した月末に送付 | 23区内契約医療機関 |
ロタテック | 生後6週から32週まで | 27日以上の間隔をあけて3回接種 | 生後1か月に達した月末に送付 | 23区内契約医療機関 |
5種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ、ヒブ)
令和6年4月1日から、5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ、ヒブ)予防接種が定期予防接種に導入されました。5種混合の詳細は、5種混合ワクチンのお知らせ(PDF 391KB)をご覧ください。
令和6年2月以降に生まれた人から5種混合の予防接種予診票を発送します。令和6年1月以前に生まれた人で接種を開始していない場合は、4月以降、お手元の4種混合の予防接種予診票で5種混合の接種が可能になります。
法定接種期間 | 標準的な接種期間と接種回数 | 予診票の送付時期 | 場所 |
|---|---|---|---|
生後2月から90月に至るまでの間 | 生後2か月~7か月になるまでの間に、20~56日の間隔をあけて3回接種。 3回目接種の終了後、6か月~18か月の間隔をあけて1回接種。 | 生後1か月に達した月末に送付 | 23区内契約医療機関 |
4種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ)
5種混合を接種した場合は、接種不要なワクチンです。
(注)4種混合ワクチンの製造中止に伴い、同じワクチンによる接種完了が困難な場合、5種混合などによる交互接種も可能です。
事前に医師に相談の上、接種してください。
法定接種期間 | 標準的な接種期間と接種回数 | 場所 |
|---|---|---|
生後2月から90月に至るまでの間 | 生後2か月~12か月になるまでの間に、20~56日の間隔をあけて3回接種。 3回目接種の終了後、6か月以上の間隔(12~18か月の間隔が望ましい)をあけて1回接種。 | 23区内契約医療機関 |
ヒブ
5種混合を接種した場合は、接種不要なワクチンです。
(注)既に4種混合とヒブワクチンに分けて接種を行なっている場合は、引き続き同じワクチンで接種を完了してください.。
法定接種期間 | 標準的な接種期間・接種回数 | 場所 |
|---|---|---|
生後2か月から60月に至るまでの間 | 生後2か月~7か月に至るまでに接種開始し、27~56日の間隔をおいて3回接種。 3回目接種後、7~13カ月の間隔をおいて1回接種。 | 23区内契約医療機関 |
急性灰白髄炎(ポリオ)
4種混合または5種混合を接種した場合は、接種不要なワクチンです。
(注)通知対象者以外で接種を希望する人は地域保健課予防接種係(03-3463-1412)までお問い合わせください。
名称 | 法定接種期間 | 標準的な接種期間と接種回数 | 場所 |
|---|---|---|---|
不活化ポリオ(急性灰白髄炎)初回 | 生後2月から90月に至るまでの間 | 生後2か月~12か月になるまでの間に20日以上の間隔をあけて3回接種(注1) | 渋谷区不活化ポリオ予防接種実施医療機関一覧(令和7年8月1日現在)(PDF 246KB) 23区内契約医療機関 |
不活化ポリオ(急性灰白髄炎)追加 | 生後2月から90月に至るまでの間 | 初回3回接種後、6か月以上の間隔をあけて1回接種 (12~18か月の間隔が望ましい)(注1) | 23区内契約医療機関(初回と同様) |
(注1)生ポリオワクチンを1回または不活化ポリオワクチン1~3回を接種している人は、合計回数が4回になるように残りの接種をします。 詳しくは、「どうすればいいの?ポリオワクチン」(PDF 375KB)をご覧ください。
BCG
詳しくは、BCGワクチンのお知らせ(PDF 904KB)をご覧ください。
法定接種期間 | 標準的な接種期間と接種回数 | 予診票の送付時期 | 場所 |
|---|---|---|---|
生後1歳に至るまで | 生後5か月~8か月になるまでの間に1回接種 | 生後4か月に達した月末に送付 | 渋谷区BCG予防接種実施医療機関一覧(令和7年7月1日現在)(PDF 170KB) 23区内契約医療機関 |
麻しん風しん混合(MR)
詳しくは、麻しん風しん混合(MR)ワクチン1期のお知らせ(PDF 278KB)、麻しん風しん混合(MR)ワクチン2期のお知らせ(PDF 172KB)をご覧ください。
名称 | 法定接種期間 | 接種回数 | 予診票の送付時期 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
麻しん風しん混合(MR)1期 | 生後12月から24月に至るまでの間 | 1回接種 | 満1歳に達する前月末に送付 | 23区内契約医療機関 |
麻しん風しん混合(MR)2期 | 小学校入学前の1年間(4月1日~翌年3月31日まで) | 1回接種 | 小学校入学1年前の3月末に送付 | 23区内契約医療機関 |
麻しん風しん混合(MR) 接種期間延長について
麻しん風しん混合(MR)ワクチンの供給不足などにより、ワクチンの接種が出来なかった人を対象に接種期間が令和9年3月31日まで延長されることになりました。(注)期限切れの予診票は使用できません。
対象者
第1期:令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれ(令和6年度内に生後24月に達した者)
第2期:平成30年4月2日~平成31年4月1 日生まれ(令和6年度における第2期の対象者)
実施期間
令和9年(2027年)3月31日まで
延長申請
電子申請 | スマート申請(麻しん及び風しん定期予防接種の接種期限延長申請)(外部サイト) から電子申請が可能です。画面を開き必要事項を入力してください。 申請には母子手帳(予防接種の記録が記載されたページ)の画像が必要です。あらかじめご用意ください。 |
|---|---|
郵送申請 | 渋谷区地域保健課予防接種係まで、下記2点をお送りください。 〒150-8010 (住所不要)渋谷区役所 地域保健課予防接種係 ・麻しん及び風しん定期予防接種の接種期限延長申請(PDF 66KB) ・母子手帳の写し(予防接種の記録部分) |
窓口申請 | 郵送申請と同様の書類を渋谷区役所7階地域保健課予防接種係窓口に提出してください。 (注)各出張所・区民センターなどでは、申請を受け付けていませんのでご注意ください。 (注)窓口での即時発行はできません。 |
(注)発送までには、申請書が到着してから5営業日かかります。(ただし申請が集中した場合は、さらに数日かかることがあります。)
水痘(水ぼうそう)
詳しくは、水痘ワクチンのお知らせ(PDF 348KB)をご覧ください。
(注)既に水ぼうそうに罹患した人は対象外です。
法定接種期間 | 標準的な接種期間と接種回数 | 予診票の送付時期 | 場所 |
|---|---|---|---|
1歳~3歳未満 | 生後12か月~15か月に1回目を接種。 1回目接種後、6か月~12か月の間隔をおいて2回目を接種。 | 満1歳に達する前月末に郵送 | 23区内契約医療機関 |
日本脳炎
詳しくは、日本脳炎1期のお知らせ(PDF 258KB)、日本脳炎2期のお知らせ(PDF 366KB)をご覧ください。
名称 | 法定接種期間 | 標準的な接種期間と接種回数 | 予診票の送付時期 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
日本脳炎1期 | 生後6月から90月に至るまでの間 | 3歳~4歳になるまでの間に、6~28日の間隔をあけて2回接種。 4歳~5歳になるまでの間に、2回目接種後から1年あけて1回接種。 | 満3歳に達する前月末に送付 | 23区内契約医療機関 |
日本脳炎2期 | 9歳~13歳未満 | 9歳の時に1回接種 | 満9歳に達する前月末に送付 | 23区内契約医療機関 |
特例接種対象者について
日本脳炎の積極的な接種勧奨を控えていた時期(平成17~21年度)の対象者は、特例対象として接種することができます。詳しくは、日本脳炎予防接種の接種スケジュール(PDF 15KB)をご覧ください。
- 平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの人:1期初回から2期までの接種を、20歳未満まで受けることができます。
予診票の発行
予診票の発行には申請が必要です。
本人確認書類をお持ちのうえ本庁舎7階 地域保健課予防接種係までお越しいただくか、電話でお問い合わせください。スマート申請(定期予防接種予診票発行申請)も受け付けています。
(注)一部の対象者には、勧奨のため予診票を郵送します。
DT二種混合(ジフテリア、破傷風)2期
詳しくは、DTワクチン2期のお知らせ(PDF 117KB)をご覧ください。
法定接種期間 | 標準的な接種期間と接種回数 | 予診票の送付時期 | 場所 |
|---|---|---|---|
11歳~13歳未満 | 11歳の時に1回接種 | 満11歳に達する前月末に送付 | 23区内契約医療機関 |
HPV(子宮頸がん予防)ワクチン
標準的な接種間隔で3回接種が完了するまでに約6か月間かかります。
詳しくは、
- 子宮頸がん予防ワクチンのお知らせ(PDF 335KB)
- これだけは知ってほしい「はじめてのHPVワクチン」(東京都作成)(外部サイト)
- 厚生労働省リーフレット(概要版)(外部サイト)
- 厚生労働省リーフレット(詳細版)(外部サイト)
- HPVワクチンに関するQ&A(厚生労働省ホームページ)
をご覧ください。
(注)接種後は体調に変化がないか十分に注意してください。詳しくは、HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ(外部サイト)をご覧ください。
(注)令和5年4月1日より、定期予防接種(公費で接種できる)HPV(子宮頸がん予防)ワクチンに9価ワクチン(シルガード9)が追加されました。詳しくは、9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について(外部サイト))をご覧ください。
法定接種期間 | 接種回数 | 予診票の送付時期 |
|---|---|---|
12歳になる年度の初日から16歳になる年度末日までの女性 (小学6年生~高校1年生相当) | 3回接種 ただし、シルガード9(9価)については、15歳の誕生日前日までに1回目の接種を行えば2回で接種完了することができる。 | 新たに接種対象者となる女性に対して4月中旬に送付。 (注)法定接種期間内であれば、手持ちの予診票で接種可能。 |
実施場所
23区内契約医療機関。
渋谷区内の契約医療機関については、渋谷区子宮頸がん予防ワクチン接種実施医療機関一覧(令和8年1月現在)(PDF 390KB)をご覧ください。
積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人への対応「キャッチアップ接種」(条件を満たす人に限り、令和8年3月31日まで)
詳しくは、積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人への対応「キャッチアップ接種」のページをご覧ください。
接種できるワクチン・接種間隔について
ワクチン | 標準的な接種間隔 | 標準的な接種間隔をとることができない場合の接種間隔 |
|---|---|---|
サーバリックス(2価) | 2回目:1回目の接種から1か月 3回目:1回目の接種から6か月 | 2回目:1回目の接種から1か月以上 3回目:1回目の接種から5か月以上かつ2回目の接種から2か月半以上 |
ガーダシル(4価) | 2回目:1回目の接種から2か月 3回目:1回目の接種から6か月 | 2回目:1回目の接種から1か月 3回目:2回目の接種から3か月以上 |
シルガード9(9価) 1回目の接種が15歳以上の人 | 2回目:1回目の接種から2か月 3回目:1回目の接種から6か月 | 2回目:1回目の接種から1か月 3回目:2回目の接種から3か月以上 |
シルガード9(9価) 1回目の接種が15歳未満の人 | 2回目:1回目の接種から6か月 | 2回目:1回目の接種から5か月以上 (注)2回目接種が5か月未満の場合は、2回目から3か月以上あけて3回目の接種が必要となる |
骨髄移植等の医療行為により免疫を失った人への予防接種再接種費用の助成
骨髄移植などの医療行為により定期予防接種の効果が期待できなくなった人を対象に、経済的負担の軽減および感染症のまん延防止を図るため、予防接種の再接種費用を助成します。
(注)再接種前と再接種後では申請書類が異なります。
(注)接種費用以外の費用(申請に要した文書発行料など)は助成対象外です。
助成対象者
下記のすべてに該当する人
- 再接種を行う日時点で、20歳未満の渋谷区民の人(注)各予防接種には再接種を受けられる年齢に上限があります。
- 骨髄移植などの医療行為により、接種済みの定期予防接種により獲得した免疫が低下または消失したため、再接種を受けることが必要であると医師に判断された人
- 定期の予防接種を規定の回数と間隔で受けている人
- 国内の医療機関で再接種を受けている人(償還払い)
助成金額
助成額は下記1、2のうち少ない方の金額
- 実際に支払った額
- 渋谷区が委託する医療機関と契約している額
対象のワクチン(子どもの定期予防接種)
- ヒブ(Hib:インフルエンザ菌b型)
- 小児用肺炎球菌
- B型肝炎
- 五種混合(DPT-IPV-Hib:ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ)
- 四種混合(DPT-IPV:ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)
- 三種混合(DPT:ジフテリア・百日咳・破傷風)
- 二種混合(DT:ジフテリア・破傷風)
- BCG(結核)
- 水痘(水ぼうそう)
- 麻しん風しん混合(MR)
- 麻しん
- 風しん
- 日本脳炎
- 不活化ポリオ(IPV)
- 子宮頸がん(HPV)
申請手順(事前申請の場合)
1.申請書の提出
下記申請書類を作成し、下記の送付先に提出してください。
2.助成対象決定
申請書類を確認し、助成対象者であると決定した場合は「決定通知書」を送付します。
3.再接種
医療機関で再接種を受けてください。
4.接種予診票は医療機関に備え置いているものをお使いいただき、費用は一度全額自己負担でお支払いください。
5.再接種費用助成請求書の提出
再接種後1年以内に費用助成請求書を地域保健課予防接種係にご提出ください。
なお、費用助成請求書は「決定通知書」送付時に同封します。
6.指定された口座へ助成金を振り込みます。
申請書類
再接種前に申請される人(事前申請)
- 【第1号様式】渋谷区予防接種再接種費用助成認定申請書(PDF:3,969KB)
- 【第2号様式】渋谷区予防接種再接種に関する医師の意見書(PDF:214KB)
- 母子健康手帳または当該履歴が確認できるものの写し(骨髄移植などの医療行為を受ける必要が生じる以前の定期の予防接種の履歴が確認できるもの)
再接種後に申請される人(償還払い)
- 【第1号様式】渋谷区予防接種再接種費用償還払い申請書兼請求書(PDF:3,969KB)
- 【第2号様式】渋谷区予防接種再接種に関する医師の意見書(PDF:214KB)
- 母子健康手帳または当該履歴が確認できるものの写し(骨髄移植などの医療行為を受ける必要が生じる以前の定期の予防接種の記録と再接種の記録が確認できるもの)
- 対象ワクチンを接種したことが分かる予防接種費用の領収書(再接種日の記録と同日のものに限る。)
(注)審査後、償還払いを決定した場合、指定の口座に振り込みます。
(注)償還払いの申請期限は、再接種を受けた日から3年以内です。
送付先
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所 地域保健課予防接種係
(注)封筒に「渋谷区予防接種再接種費用助成認定申請書在中」と明記してください。
外国語版予防接種のご案内
「予防接種と子どもの健康 Vaccination and Children’s Health」
各予防接種の英語版の説明が必要な人は、「公益財団法人予防接種リサーチセンター」をご参照ください。 公益財団法人 予防接種リサーチセンター「Vaccination and Children's Health」(外部サイト) |
「定期予防接種の種類 Childhood Immunizations」
相談窓口
接種前の相談
内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|
副反応への懸念など、医学的な内容について | かかりつけ医、接種を予定する医療機関 |
HPVワクチンを含む予防接種、その他感染症全般について | 厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口(電話: 03-5656-8246) |
対象者、接種期間、実施医療機関、予診票の再発行などについて | 渋谷区保健所 地域保健課予防接種係(電話:03-3463-1412) |
接種後の相談
内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|
体調不良などの気になる症状、医学的な内容について | かかりつけ医、接種を予定する医療機関 |
HPVワクチンを含む予防接種、その他感染症全般について | 厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口(電話: 03-5656-8246) |
接種後の不安や疑問について | 東京都保健医療局 感染症対策部防疫課(電話:03-5320-5892) |
予防接種健康被害救済制度について | 渋谷区保健所 地域保健課予防接種係(電話:03-3463-1412) |
お問い合わせ
地域保健課予防接種係
電話 | 03-3463-1412 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4937 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1412
電話
FAX
03-5458-4937
お問い合わせ
関連コンテンツ
里帰り出産などにより23区外で接種した子どもの定期予防接種費用の助成
定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて(厚生労働省のホームページ)
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省のホームページ)
ポリオの予防には、ポリオワクチンの接種が必要です。(厚生労働省のホームページ)
ポリオとポリオワクチンの基礎知識Q&A(厚生労働省のホームページ)
小児用肺炎球菌ワクチンの切替えに関するQ&A(厚生労働省のホームページ)
B型肝炎ワクチンに関するQ&A(厚生労働省のホームページ)
子宮がん検診を受診しましょう
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)(厚生労働省のホームページ)
積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人への対応「キャッチアップ接種」
子どもの定期予防接種予診票の交付・再交付申請(期限延長を除く) の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能