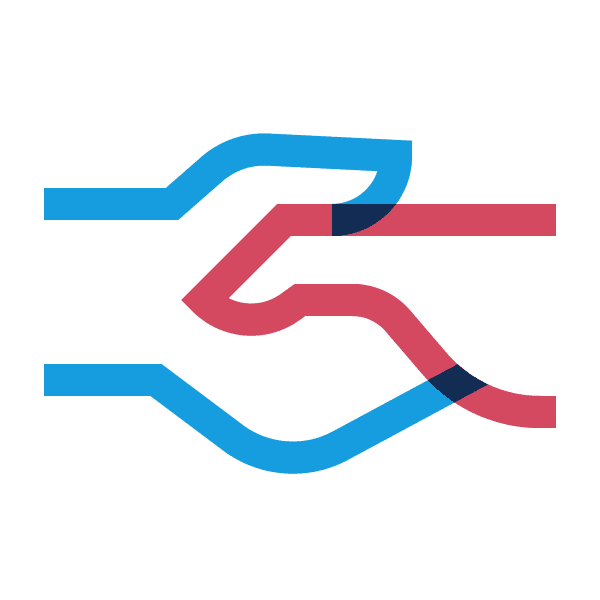サービスを利用できる人
要支援・要介護の認定を受け、介護が必要であると判定された人が介護サービスを利用することができます。
サービスを利用できる人は、それぞれの被保険者において次のとおりです。
第1号被保険者(65歳以上の人)
寝たきりや認知症などで、入浴・排泄・食事などの日常生活動作において常に介護を必要とする人、または家事などの日常生活に支援が必要な人
第2号被保険者(40~64歳の医療保険加入者)
加齢に伴う次の16の特定疾病により、介護や日常生活の支援が必要な人
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護サービスを利用するまでの手順
寝たきりや認知症などで、介護や日常生活の支援が必要になったときは、要介護・要支援認定の申請が必要です。
認定の申請
お住まいの地域を担当する地域包括支援センターまたは介護保険課介護認定係の窓口へ申請してください。
本人・家族のほか、居宅介護支援事業者や介護保険施設等が代行して申請することもできます。
必要なもの
- 新規申請書(PDF 527KB)
- 調査連絡票(PDF 60KB)
- 医療保険加入関係がわかるもの(40歳から64歳までの第二号被保険者のみ)
(注)下記の「第二号被保険者(40歳から64歳)医療保険加入関係の確認方法」の案内に従い必要なものをご用意ください。
第二号被保険者(40歳から64歳)の医療保険加入関係の確認方法
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することから、第二号被保険者の医療保険加入関係の確認方法について変更となります。
(注)ただし、現行の健康保険証が利用可能な令和7年12月1日まで(健康保険証の有効期限が令和7年12月1日以前の場合はそれ以前まで)は、現行通り健康保険証を使用しご申請いただけます。
窓口で申請する場合
- 被保険者本人による申請
次の1・2のいずれかをご用意ください。
- マイナ保険証とマイナポータル「医療保険の資格情報画面」をご提示ください。職員にて内容確認いたします。
- 医療保険者の発行する「資格確認書」のご提示、またはコピーをご提出ください。
- 代理人による申請
医療保険者の発行する「資格確認書」のご提示、またはコピーをご提出ください。
郵送・オンラインで申請する場合(区役所介護保険課で受理した日が申請日になります)
医療保険者の発行する「資格確認書」のコピー・画像をご提出ください。
オンラインでの申請も受け付けております。
詳しくは、要介護認定・要支援認定オンライン申請手順書(PDF 574KB)をご覧ください。
(注)申請フォームへのリンク先も要介護認定・要支援認定オンライン申請手順書(PDF 574KB)に記載があります。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
認定調査
調査員が訪問し、心身の状態や日常生活の状況などについて面接調査します。
審査判定
認定調査票と主治医意見書の内容から、コンピューターによる一次判定を行います。
一次判定の結果、認定調査票の特記事項、主治医意見書から「介護認定審査会」で審査判定し、原則として30日以内に認定を行います。
急を要する場合は、認定結果が出る前にサービスを利用することができますので、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターにご相談ください。
認定
要支援、要介護、自立(非該当)の認定がされます。
認定の種類と利用できるサービス
認定の種類 | 利用できるサービス |
|---|---|
要支援1・2 | 介護予防サービス(介護予防給付)、介護予防・生活支援サービス事業 |
要介護1・2・3・4・5 | 介護サービス(介護給付) |
自立(非該当) | 区のサービス(介護保険サービスの利用対象にはなりません) |
介護サービス計画(ケアプラン)作成
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者の希望や心身の状態に合わせて効率的にサービスを利用できるよう、 ケアプランを作成します。
本人がケアプランを作成することもできます。
作成費用は、全額介護保険でまかなわれるため、料金はかかりません。
「要支援1・2と認定された人」
地域包括支援センターに、 介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
「要介護1~5と認定された人」
居宅介護支援事業者を選んで、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
事業者を通して、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」もしくは「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能・看護小規模多機能)」を区へ提出してください。詳しくは居宅サービス計画の届出・介護サービス計画等作成資料の提示申請についてのページをご覧ください。
どのような事業者があるかを、地域包括支援センターで案内しています。
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)保健・医療・福祉サービス従事者のうち、一定の実務経験があり、試験に合格した後に実務研修を終了した人が担当します。
利用者からの相談に応じて、利用者の希望や心身の状態にあったサービスが利用できるよう、区、在宅サービス事業者、 介護保険施設などとの連絡や調整を行います。居宅介護支援事業者に所属して活動します。地域包括支援センターにもいます。
サービス提供事業者との契約
ケアプランが決定したら、サービス事業者と契約書を取り交わし、介護サービスの利用が始まります。
安心して介護サービスを利用するために、事業者やサービス内容については慎重に検討し、十分に納得したうえで選択してください。
介護保険事業者を選ぶのに迷ったときは、区内介護保険事業者の情報を掲載した「介護サービス事業者ガイドブック(ハートページ)」をご利用ください。地域包括支援センター、区役所2階福祉手続き・相談のフロアで無料で配付しています。
介護サービスの利用
利用時には、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を、サービス提供事業者に提示します。 原則として、サービス利用費用の1割または2割(平成30年8月より、一定以上所得のある方は3割)を支払います。利用上限額を超えた分は全額自己負担となります。
更新申請と区分変更申請
認定有効期間について
要介護認定・要支援認定には、下表のとおり有効期間があります。
申請区分 | 認定区分 | 認定の有効期間 | 審査会の意見により、延長・短縮が行われる期間 |
|---|---|---|---|
新規申請 | 要支援・要介護 | 原則 6か月 | 3~12か月 |
更新申請 | 要支援 | 原則12か月 | 3~36か月 |
更新申請 | 要介護 | 原則12か月 | 3~36か月 |
区分変更申請 | 要支援・要介護 | 原則 6か月 | 3~12か月 |
更新申請
介護サービスを引き続いて利用したい場合は、有効期間内に認定の更新が必要です。
更新申請手続の書類は、認定有効期間の切れる60日前に送付します。有効期間が切れる前に、
お住まいの地域を担当する地域包括支援センターまたは介護保険課介護認定係に申し込んでください。
必要なもの
- 更新申請書(PDF 527KB)
- 調査連絡票(PDF 61KB)
- 医療保険加入関係がわかるもの(40歳から64歳までの第二号被保険者のみ)
(注)下記の「第二号被保険者(40歳から64歳)医療保険加入関係の確認方法」の案内に従い必要なものをご用意ください。
第二号被保険者(40歳から64歳)の医療保険加入関係の確認方法
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することから、第二号被保険者の医療保険加入関係の確認方法について変更となります。
(注)ただし、現行の健康保険証が利用可能な令和7年12月1日まで(健康保険証の有効期限が令和7年12月1日以前の場合はそれ以前まで)は、現行通り健康保険証を使用しご申請いただけます。
窓口で申請する場合
- 被保険者本人による申請
次の1・2のいずれかをご用意ください。
- マイナ保険証とマイナポータル「医療保険の資格情報画面」をご提示ください。職員にて内容確認いたします。
- 医療保険者の発行する「資格確認書」のご提示、またはコピーをご提出ください。
- 代理人による申請
医療保険者の発行する「資格確認書」のご提示、またはコピーをご提出ください。
郵送・オンラインで申請する場合(区役所介護保険課で受理した日が申請日になります)
医療保険者の発行する「資格確認書」のコピー・画像をご提出ください。
区分変更申請
有効期間内に、心身の状態が急激に変化した場合などは、要介護状態区分の変更申請ができます。
お住まいの地域を担当する地域包括支援センターまたは介護保険課介護認定係に申し込んでください。
必要なもの
- 区分変更申請書(PDF 526KB)
- 変更理由書(WORD 16KB)
- 調査連絡票(PDF 60KB)
- 医療保険加入関係がわかるもの(40歳から64歳までの第二号被保険者のみ)
(注)下記の「第二号被保険者(40歳から64歳)医療保険加入関係の確認方法」の案内に従い必要なものをご用意ください。
第二号被保険者(40歳から64歳)の医療保険加入関係の確認方法
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することから、第二号被保険者の医療保険加入関係の確認方法について変更となります。
(注)ただし、現行の健康保険証が利用可能な令和7年12月1日まで(健康保険証の有効期限が令和7年12月1日以前の場合はそれ以前まで)は、現行通り健康保険証を使用しご申請いただけます。
窓口で申請する場合
- 被保険者本人による申請
次の1・2のいずれかをご用意ください。
- マイナ保険証とマイナポータル「医療保険の資格情報画面」をご提示ください。職員にて内容確認いたします。
- 医療保険者の発行する「資格確認書」のご提示、またはコピーをご提出ください。
- 代理人による申請
医療保険者の発行する「資格確認書」のご提示、またはコピーをご提出ください。
郵送・オンラインで申請する場合(区役所介護保険課で受理した日が申請日になります)
医療保険者の発行する「資格確認書」のコピー・画像をご提出ください。
オンラインでの申請も受け付けております。
詳しくは、要介護認定・要支援認定オンライン申請手順書(PDF 573KB)をご覧ください。
(注)申請フォームへのリンク先も要介護認定・要支援認定オンライン申請手順書(PDF 573KB)に記載があります。
認定申請の取下げ
要介護認定・要支援認定申請(新規・更新・区分変更)を行った後、以下の理由などで申請の取下げを希望する場合、申請取下げ届の提出が必要となります。
- 状態改善などにより介護認定の必要がなくなったとき
- 認定を受ける対象者が調査前に死亡したとき
- 書類上の不備がわかったとき(誤った申請区分で申請を行ってしまった場合など)
原則、申請を行った人から事前に介護認定係(03-3463-2016)にご連絡のうえ、介護保険課介護認定係へご提出ください。
必要なもの
死亡時の手続き
介護保険の被保険者が亡くなったときは、介護保険被保険者証などを返却してください。
【返却先】渋谷区役所本庁舎5階介護保険課窓口(注)、出張所・区民サービスセンター、地域包括支援センター
(注)郵送も可。あて先:〒150-8010(住所不要)渋谷区役所介護保険課
お問い合わせ
介護保険課介護認定係
電話 | 03-3463-2016 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4934 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2016
電話
FAX
03-5458-4934
お問い合わせ
要介護認定・要支援認定申請 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能