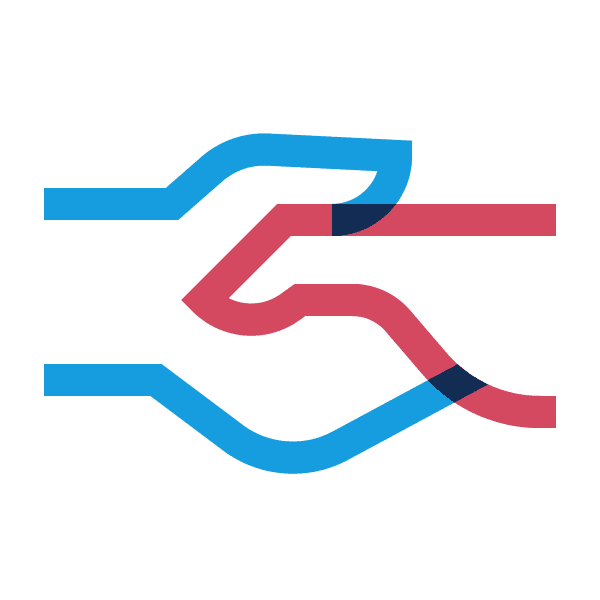
風しん追加的対策(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性対象)
風しんの予防接種を受ける機会が無かった年代の男性を対象に、風しんの予防接種を実施します。
更新日
2025年12月8日
お知らせ
2025年4月1日
令和7年3月末までに抗体検査を受けた人は、ワクチン接種期間が令和9年3月31日まで延長されます。(注)検査の結果、風しんの抗体が不十分だった人が対象
期間内に予防接種が受けられなかった人への予防接種期限延長について
(注)令和7年3月末までに抗体検査を受けた人で、風しんの抗体が不十分だった人が対象
麻しん風しん(MR)ワクチンの供給不足により、ワクチンの接種が出来なかった人を対象に接種期間が令和9年3月31日まで延長されることになりました。
(注)期限切れのクーポン券は使用できません。
(注) 延長は予防接種事業のみで風しん抗体検査事業は延長されておりませんので、ご注意ください。
対象者
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和7年3月末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な人
(注)令和7年4月以降、抗体検査をした人は対象外
(注)HI法で8倍以下、EIA法で6.0未満の人です。HI法・EIA法以外の基準値は抗体価一覧表でご確認ください。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
実施期間
令和9年(2027年)3月31日まで
費用
1人につき1回まで、予防接種が無料で受けられます。
使用ワクチン
麻しん風しん(MR)ワクチン または 風しん単体ワクチン
実施方法
クーポン券がお手元に届きましたら、指定の医療機関などへ事前にご予約の上、受診してください。
クーポン券利用時の注意
クーポン券には有効期限があります。有効期限までに指定の医療機関などで受診してください。
渋谷区を転出された場合は、このクーポン券は使用できません。お住まいの市区町村の担当窓口に問い合わせてください。
持ち物
風しん予防接種
- クーポン券
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 風しん抗体検査受診票(本人控え)など、抗体価が基準値より低いことを確認できる書類
対象の医療機関
接種場所は渋谷区内の契約医療機関です。
延長手続きについて
電子申請 | スマート申請(麻しん及び風しん定期予防接種の接種期限延長申請)(外部サイト) から電子申請が可能です。画面を開き必要事項を入力してください。 申請には風しん抗体検査の結果が分かる書類の画像が必要です。あらかじめご用意ください。 |
|---|---|
郵送申請 | 渋谷区地域保健課予防接種係まで、下記2点をお送りください。 〒150-8010 (住所不要)渋谷区役所 地域保健課予防接種係 ・麻しん及び風しん定期予防接種の接種期限延長申請(PDF 66KB) ・風しん抗体検査の結果が分かる書類(注)渋谷区のクーポン券以外で実施した抗体検査の場合は実施日と抗体値が分かる画像を添付してください。 |
窓口申請 | 郵送申請と同様の書類を渋谷区役所7階地域保健課予防接種係窓口に提出してください。 (注)各出張所・区民センターなどでは、申請を受け付けていませんのでご注意ください。 (注)窓口での即時発行はできません。 |
(注)発送までには、申請書が到着してから5営業日かかります。(ただし申請が集中した場合は、さらに数日かかることがあります。)
検査結果がHI法16倍またはEIA法6.0以上8.0未満の人へ
抗体検査の結果、HI法16倍またはEIA法6.0以上8.0未満の人は、定期予防接種の対象ではありませんが、妊娠を希望する女性の同居者または妊婦の同居者は、渋谷区で行っている風しん予防接種費用助成を受けることができます。詳しくは、風しん抗体検査が無料で受けられますのページをご覧ください。
副反応について
主な副反応は、発熱や、発しんです。これらの症状は、接種を受けた後5日から14日の間に多くみられます。接種を受けた直後から翌日に過敏症状と考えられる発熱、発しん、掻痒(かゆみ)などがみられることがありますが、これらの症状は通常1日から3日でおさまります。
ときに、接種を受けた部位が赤くなったり、腫れたり、しこりや、リンパ節の腫れなどができたりすることがありますが、いずれも一過性で通常数日中に消失します。
まれに重大な副反応として、「ショック・アナフィラキシー様症状(血圧低下、呼吸困難、顔面蒼白など)」、「急性散在性脳脊髄炎(ADEM)」、「脳炎・脳症」、「けいれん」、「血小板減少性紫斑病(紫斑、鼻出血、口腔粘膜の出血など)」などが報告されています。
予防接種健康被害救済制度について
本対策での予防接種は、予防接種法に基づく予防接種(定期予防接種)です。万一、健康被害が発生した場合は、予防接種健康被害救済制度の対象となります。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
【医療機関向け】風しんの追加的対策に係る令和7年度から令和9年度実施分の請求について
国保連合会が代行する、集合契約における請求・支払事務は令和7年3月10日(必着)をもって終了しました。
3月10日以降に委託料を請求する場合は、クーポン券発行の自治体の保健所に直接請求してください。
請求方法
(注)予防接種の請求書と抗体検査の請求書様式は異なります。
(注)対象者が渋谷区民の場合と渋谷区民以外の場合で請求先が異なります。
(参考)風しん追加対策請求方法(PDF 647KB)
渋谷区民【予防接種請求書】
- 【予防接種】風しん対策市区町村別請求書(Excel 30KB)(必要事項を入力後、印刷して代表印を押印し、請求書を作成する。)
- クーポン券が貼付された受診票または予診票
渋谷区民【抗体検査請求書】 (注)抗体検査は令和7年2月末実施までのものに限る
- 【抗体検査】風しん対策市区町村別請求書(Excel 38KB)(必要事項を入力後、印刷して代表者印を押印し、請求書を作成する。)
- クーポン券が貼付された受診票または予診票
送付先
〒150‐8010(住所不要)渋谷区役所 地域保健課 予防接種係 宛
渋谷区民以外
クーポン券発行元の自治体へ直接、お問い合わせください。
お問い合わせ
地域保健課予防接種係
電話 | 03-3463-1412 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4937 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1412
電話
FAX
03-5458-4937
お問い合わせ
