- TOP
- 子育て・教育・生涯学習
- 青少年育成
- 青少年育成
現在のページ
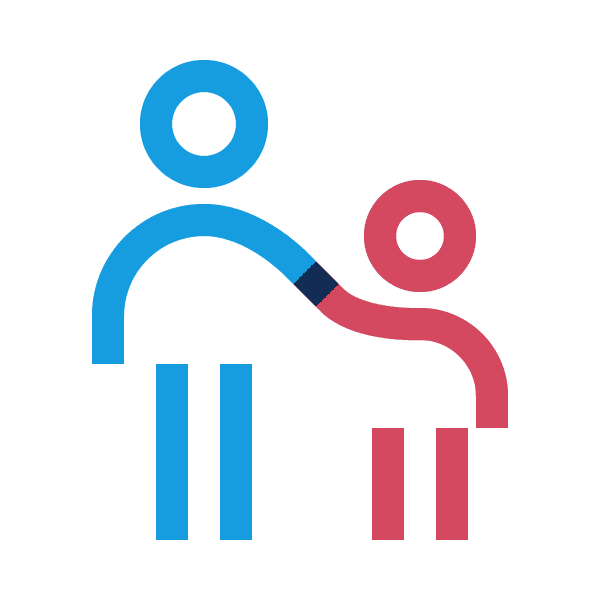
犯罪から子どもを守るために こんなとき、あなたはどうしますか
子どもを犯罪から守るために、日ごろの準備についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
子どもを犯罪から守るためには、日ごろの準備が大切です。家庭で、地域で、子どもと一緒に考えてみましょう。
知らない人からの電話には
- 相手が知り合いだと言っても、「親から電話をします。連絡先を教えてください。」と言って、質問には答えない。
- 変な電話がかかってきたときは、「わかりません」「答えられません」などと答え、すぐに電話を切り、必ず親や学校などに連絡する。
家庭では
知らない人からの電話は、「わかりません」と言ってすぐ切るようにするなど、不審な電話への対応ができるように練習しておきましょう。
家にひとりでいるとき
- 玄関のカギをかけて、知らない人を中に入れない。
- 知らない人が入ってきたら、外に出て助けを呼ぶ。
- 知らない人から電話がかかってきても、「家の人がすぐ帰ってくる」などと答え、長い時間ひとりでいることを知られないようにする。
家庭では
留守番時の訪問者に対しては、のぞき穴やドアチェーンを利用し、すぐに出ないようにします。
保護者は、ときどき家に連絡を入れるなどして、安全確認をするようにしましょう。
保護者の不在を電話などで確認し、強盗に入るケースがあります。電話の応対に気をつけましょう。
地域では
日ごろから隣近所や地域で、防犯体制についてよく話し合っておきましょう。
助けを求められたら、すぐに保護し、110番へ通報するなどの対処をしましょう。
エレベーターに乗るとき
- なるべくひとりでは乗らない。
- 変だと思う人が乗ってきたら、自分の降りる階でなくてもすぐに降りる。
- 階数ボタンや非常ボタンを押せるところに乗る。
- 体をさわられたりしたら、非常ボタンやすべての階のボタンを押し、大声を出して助けを求める。
家庭では
エレベーターには、なるべく知っている人と乗るよう、日ごろから話しておきましょう。
非常ボタンの位置や使い方を教えておきましょう。
地域では
エレベーターに防犯カメラを設置するようにし、ホールなどに防犯ポスターを貼りましょう。
エレベーターのある高層住宅の周りや外階段などをパトロールするようにしましょう。
公園や広場で遊ぶとき
- 公園や広場ではひとりで遊ばない。
- 人のいない所や「立入禁止」の場所には、絶対に行かない、入らない。
- 公園のトイレには、ひとりで行かない。
- 遊ぶ場所、帰る時間を家の人に知らせておき、時間を守る。
家庭では
危険な場所を確認しておき、子どもに行かないように教えましょう。
どんな遊びをしたのかなど、ふだんから子どもの話をよく聞くようにしましょう。
地域では
地域の危険箇所をリストアップして、家庭や学校へ報告しましょう。
危険な場所には「立入禁止」などの表示をして、付近のパトロールを行いましょう。
知らない人につきまとわれたとき
- 物をくれると言われても、絶対についていかない。
- いつまでもついて来たり、追いかけられたりしたら、防犯ベルを鳴らし、近くの人や店、交番に助けを求める。
- または、走って逃げる。
- すぐ近くの電話で「110番」をする。(110番は10円やテレホンカードがなくてもかかります)
家庭では
ゲームソフトなど、子どもが興味や関心のあるものを見せて、誘い出す手口があります。ただでくれる、買ってあげると言われても、絶対にもらってはいけない、ついていってはいけないと話しましょう。
人通りの少ない道は、歩かせないようにしましょう。
帰宅時間を決めて、必ず守らせるようにしましょう。
地域では
夕方遅くまで遊んでいる子どもがいたら、帰宅するよう、声かけをしましょう。
また、「こども110番の家」事業に協力するなど、地域での防犯体制をつくりましょう。
だれもいない家にひとりで帰るとき
- 誰かついてくる人がいないことを確かめてから、家のカギを開けるようにする。
- 家に誰もいなくても、大きな声で「ただいま」と言い、入ったらすぐにカギをかける。
- 知らない人が来ても、ドアを開けない。郵便や宅配便の人が来たときも、すぐにドアを開けずに、様子を見てから開ける。
家庭では
留守にする場合は、近所にひと声かけておきましょう。
カギを持たせるときは、カバンにぶら下げるなどは危険です。見えない場所につけてください。
普段から施錠の習慣を身につけて、誰かが訪ねてきても、すぐにカギを開けないよう教えましょう。
地域では
留守にする家庭から声をかけられたときは、子どもの帰宅に気を配ってあげましょう。
車に乗った人から声をかけられたとき
- 知らない人の車には絶対に乗らない、近づかない。
- 道を聞かれたら、その場で教え、「家まで送ってあげる」と言われても、絶対に車に乗らない。
- 体をつかまれたり、むりやり連れて行かれそうになったら、大声で助けを求めたり、近くの「こども110番の家」のプレートがある家や店まで逃げる。
家庭では
知らない人の車には不用意に近づかないように教えしょう。
ひとりでの行動は避け、友だちと一緒に登下校させましょう。万が一、身の危険を感じたら、「こども110番の家」や近くの店に逃げ込むよう教えましょう。
子どもには、身の危険を感じるようなことがあったら、必ず報告させましょう。
地域では
子どもに声をかけている不審な車(人)を見かけたら、「どうしたの?」など、声をかけましょう。
助けを求められたら、子どもを保護し110番通報をします。そのとき、車のナンバーを控えておきましょう。
夕方には、門灯などを早めにつけて、街を明るくすることも大切です。
学校や幼稚園、保育園などに不審な人が入ってきたとき
- すぐに、先生や近くにいる大人に知らせる。
- 周りに先生や大人がいないときは、いるところまで行って知らせる。
- 自分や友だちが、追いかけられたり抱きつかれたりしたら、大声を出し防犯ベルを鳴らして、周りの人に助けを求める。
家庭では
不審者や見知らぬ人を見かけたら、まず、近くにいる先生や大人に知らせるよう、話しましょう。
近くに大人がいないときには、消防用の非常ベルや防犯ベルなど、大きな音の出るもので人を呼ぶように教えましょう。
また、襲われたときには、「走って逃げる」「大声を出す」などで対処するように教え、練習をしておくことが大切です。
地域では
不審者が学校や幼稚園、保育園などに入るのを見かけたら、声をかけるようにしましょう。
地域パトロールを積極的に行い、不審者を見かけたときは、警察や近隣の学校、幼稚園、保育園などに連絡しましょう。
小中学生は
配られた防犯ブザーをいつも身につけて、危ないときには鳴らすことができるようにしておきましょう。
お問い合わせ
子ども青少年課子ども青少年育成係
電話 | 03-3463-2578 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4942 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2578
電話
FAX
03-5458-4942
お問い合わせ
