- TOP
- スポーツ・文化・観光
- 文化財・観光
- 文化財・名所
現在のページ
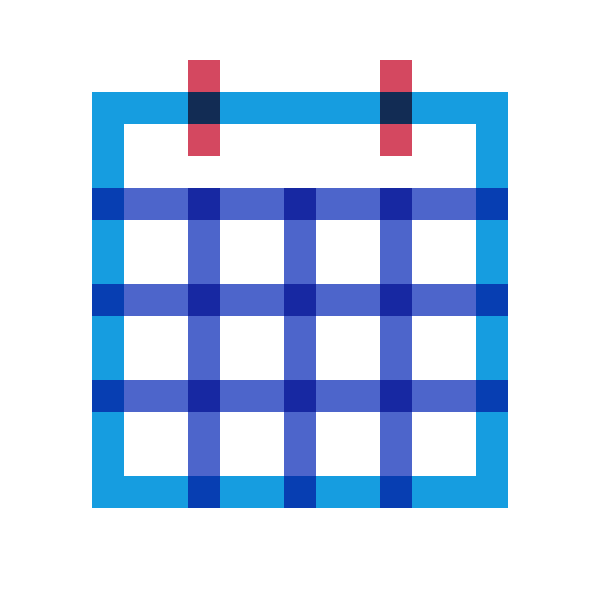
文化人の碑
文化人の碑についてのご案内です
更新日
2024年9月25日
区内にはかつて、多くの文化人が住み、渋谷の自然や風景を、書物や絵画に残してきました。そうした著名な文化人の住居跡や記念碑、また終えんの地などの碑を区内でも見ることができます。
国木田独歩住居跡
宇田川町7-21
国木田独歩は、明治29年9月から、山路愛山の紹介でこの地に住みました。
当時このあたりは、小川や林などの自然が豊かでした。
ここでの生活や風光をもとに、有名な「武蔵野」などの名作を書きました。
竹久夢二居住地跡
宇田川町31-2
詩人でもある竹久夢二は、独特の作風による美人画家としても有名です。
明治17年に岡山県に生まれ、大正 10年8月から大正13年12月までここに住み、「どんたく図案社」「一草居」の表札を出して画業にはげみました。
山路愛山終えんの地
宇田川町13-11
山路愛山は明治の歴史評論家で、明治29年6月から大正6年3月15日に54歳で亡くなるまでこの地に住み、独特の歴史評論活動を展開しました。
代表作には「豊大閣」「西郷隆盛」「足利尊氏」などがあります。
東京新詩社跡
道玄坂2-6
明治34年、詩人与謝野鉄幹は、麹町からここに移り住み、晶子と結婚しました。
この地から機関紙「明星」を発刊したり、晶子も歌集「みだれ髪」を刊行しました。
明治37年晶子が「君死に給ふことなかれ」を発表したことから、千駄ヶ谷1丁目に移りました。
与謝野晶子歌碑、道玄坂道供養碑、由来碑
道玄坂2-10
道玄坂を上っていくと、左手に三つの碑が並んでいます。
与謝野晶子歌碑には「母遠うて瞳したしき西の山 相模か知らず雨雲かかる」とあります。
田山花袋終えんの地
代々木3-9-5
田山花袋は、明治39年にここ移り住み、昭和5年に60歳でこの地で亡くなりました。
「田舎教師」「蒲団」などの名作のほか、「東京の三十年」の中では明治時代の渋谷の様子も記しています。
高野辰之住居跡
代々木3-3
国文学者として有名な高野辰之は、明治42年からこの地に住みました。
ここに流れていた河骨川をイメージして文部省唱歌「春の小川」を作詞しました。
菱田春草終えんの地
代々木3-47-1
明治末期の日本画壇で活躍した菱田春草は、明治41年に代々木山谷に住み、同44年にこの地の移り住みました。
そして、「落ち葉」「黒き猫」「早春」などの名作を発表しました。
新井白石終えんの地
千駄ヶ谷6
新井白石は、6代将軍徳川家宣、7代将軍家継の2人の将軍に儒学者として仕えましたが、政治に携わったことから、8代将軍吉宗の代に失脚し、官邸は没収され、千駄ヶ谷のこの地に移り住んで著作に専念し、享保10 年(1725)5月19日に亡くなりました。
著作の中でも「折焚柴木」「藩翰譜」「采覧異言」は有名です。
東京新詩社跡(第四萩の家跡)
千駄ヶ谷1-23-3
明治37年11月、与謝野鉄幹・晶子夫妻は道玄坂からこの地に移り住みました。
この頃が東京新詩社の活動の最盛期でした。
徳冨蘆花住居跡
神宮前4-9-5
明治の文豪徳冨蘆花は、明治33年に逗子からここに移り、同38年に再び逗子に戻るまでの間に「思出の記」を完成させました。
また、「黒潮」「慈悲心鳥」「霜枯日記」などの作品も発表しました。
松崎慊堂宅地跡
東4-9-1
松崎慊堂は江戸後期の学者で、32歳のときに掛川藩に招かれ藩政に参加しましたが、故郷である肥後藩の誘いを断り、この地に山荘を造り「石経山房」と名付け、学問研究と門弟の教育にあたり、弘化元年(1844)に74 歳で亡くなるまでここに住みました。
服部南郭別邸跡
東2-10-4
服部南郭は、江戸中期の儒学者で、柳沢吉保に仕えました。
また、荻生徂徠の門人として古文辞学と詩を学びました。
その後この地で私塾を開き後進の指導にあたり、宝歴9年(1759)77歳で亡くなりました。
旧三宅雪嶺邸三宅文庫(東京都指定有形文化財)
初台2-27-14
三宅雪嶺は、明治から昭和にかけて活躍した評論家・思想家で、初台坂を下った左側に住居地跡があります。
当時の木造の母屋は戦災で失われ、現在はコンクリート造りの文庫だけが残っています。
岡田三郎助終えんの地
恵比寿3-35-10
岡田三郎助は、明治から昭和にかけて活躍した洋画家です。
黒田清輝らの影響を受け「北国の五月頃」をはじめ多くの名作を残しました。
東京芸術大学の教授でもあり、第1回文化勲章を受章し、昭和14年(1939)71歳で亡くなりました。
区内にある芭蕉句碑
「眼にかかる 時や殊更 さ月不二」
御嶽神社 渋谷1-12-16
「しばらくは 花の上なる 月夜か那」
金王八幡宮 渋谷3-5-12
「暮おそき 四谷過ぎけり 紙草履」
荘厳寺 本町2-44-3
「春もやや けしきととふ 月と梅」
竜巖寺 神宮前2-3-8
竜巖寺の芭蕉句碑は、戦災により上部が半分ほど焼失しています。
お問い合わせ
文化振興課文化財主査
電話 | 03-3486-2792 |
|---|---|
FAX | 03-3486-2793 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3486-2792
電話
FAX
03-3486-2793
お問い合わせ
