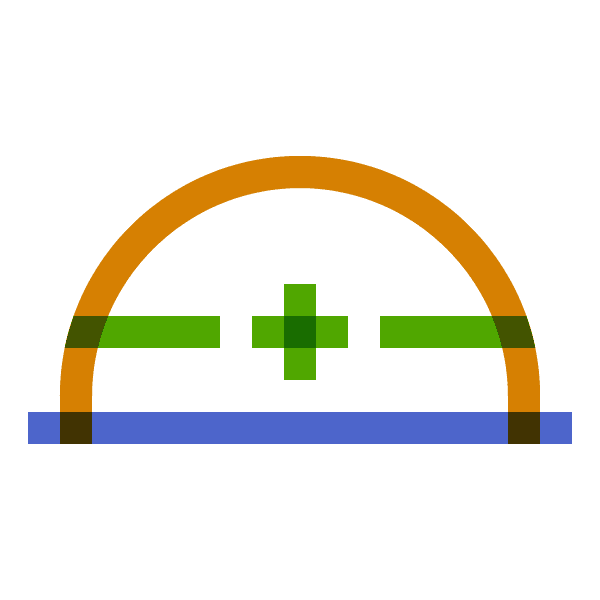災害時に、要配慮者(高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者)は、ひとりで身の安全を確保し、避難行動に移ることが容易ではありません。 生き埋めや火災・けが人が同時に多くの場所で発生する震災では、消防や警察といった機関も、すぐにすべての現場に出動することは困難です。家族はもちろん、近隣に住む人たちが安否を確認し、避難行動などを支援する必要があります。
避難行動要支援者とは
渋谷区では、要配慮者のうち災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する者を「避難行動要支援者」と定め、「避難行動要支援者名簿」を作成して、自主防災組織(町会)をはじめとする関係機関へ配付し、災害時の避難支援に備えています。
避難行動要支援者名簿の登録要件
- 自動登録 [本人の意思表示によらず、区が次に該当する人を抽出し登録する]
- 区内在住の単身世帯者で、介護保険法に基づく要介護2以上の要介護認定を受けている者
- 区内在住の単身世帯者で、身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳2級以上の交付(視覚障害、下肢障害、体幹障害に限る)を受けている者
- 渋谷区高齢者保健福祉計画で定めるセーフティネット見守りサポート事業に登録している者
- 任意登録 [本人の意思に基づき登録する(手上げ方式)]
- 区に申請し、承認を受けた者(福祉施設などに入居している人を除く)
(注)年齢、性別、世帯の状況、介護度や障害の種類などの条件はありません。家族と同居していても、本人と家族の力だけでは避難が困難な場合は、名簿登録の対象となります。
ただし、本人が一人で避難できると区が判断した場合は、登録できない場合があります。
申請方法
避難行動要支援者名簿登録申請書(WORD 20KB)に必要事項を記入のうえ、〒150-8010 宇田川町1-1 渋谷区役所 高齢者福祉課 福祉避難所対策担当主査 へ郵送・持参してください。
(注)名簿作成の都合上、当該年度の2月末までに申請書を提出した場合、翌年度の名簿登録の候補となります。
支援のしくみ
1 | 4月頃に区が避難行動要支援者名簿を作成・更新し、6月頃に自主防災組織などの関係機関へ配付する。 |
|---|---|
2 | 自主防災組織が中心となり、民生児童委員、安心見守りサポート協力員とともに避難行動要支援者の自宅を訪問し、本人や家族と相談して近隣の避難支援者、避難先、避難方法などを決定し、「個別避難計画」を作成する。 |
3 | 以下のメンバーで「個別避難計画」を共有する。 ・要援護者本人(または家族) ・避難支援者(=実際に支援する近隣住民など) ・(注)自主防災組織代表者 ・(注)民生児童委員 ・(注)安心見守りサポート協力員 ・地域包括支援センター ・区 (注)は「個別避難計画」作成者、作成者が区に計画書を提出 |
4 | 災害発生時には、「個別避難計画」に基づき、避難支援者を中心に避難行動要支援者の安否確認や避難支援を行う。(ただし、避難支援者本人とその家族の安全確保が前提となるので、計画どおりの支援が保証されるものではなく、避難支援者も法的責任や義務を負うことはありません。) |
渋谷区では、避難行動要支援者の皆様に対して、在宅避難や備蓄の重要性、避難行動要支援者名簿や個別避難計画などの制度を分かりやすくお知らせするため、「渋谷区避難行動要支援者ハンドブック(PDF 2,105KB)」を作成しています。
(参考)個別避難計画書の様式(WORD 36KB)
名簿の管理
保存先 | 目的 |
|---|---|
自主防災組織代表者 民生児童委員 安心見守りサポート主任協力員 | 避難行動要支援者の自宅を訪問して「個別避難計画」を作成し、近隣住民による支援体制を確立するため。 ・左記の人は「計画作成者」となりますが、「避難支援者」を兼ねる場合もあります。 |
地域包括支援センター | 避難行動要支援者の情報を共有するため。 |
渋谷消防署 渋谷消防団 区内の警察署 | 災害発生時の救出・救助活動に活用するため。 ・消防署員、消防団員、警察署員が救出・救助に来ることを保証するものではありません。 |
(注)上記以外にも、区の規則に基づき社会福祉施設などで保管する場合があります。
(注)いずれの保管先も、名簿情報が漏えい・拡散しないよう適正に管理しています。
お問い合わせ
福祉避難所対策担当主査
電話 | 03-3463-1562 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4941 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1562
電話
FAX
03-5458-4941
お問い合わせ